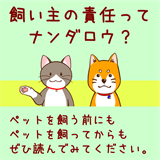ペットのマイ避難カードをつくろう!
兵庫県では、「マイ避難カード」の作成を推進しています。(参考: 兵庫県災害対策課「マイ避難カード」 )
家族とペットのための災害対策について、家族会議で話し合った結果を、ペットバージョンの「ペットのマイ避難カード」に記入しましょう。
そして、作成したカードは、家族みなさんがよく見える場所に掲示しておき、防災意識を高めましょう。
【関係ページ】
▶ペットの災害対策
▶ペット健康防災手帳をつくろう!
「ペットのマイ避難カード」とは
災害の危険が迫っている時に、迷わず行動できるように、「だれが」「いつ」「どこに」「どのように」ペットと一緒に避難するかをあらかじめ家族で確認・点検し、書き記したものです。
「ペットのマイ避難カード」作成の目的
自然災害では「自分の命もペットの命も自分(飼い主)で守る」ことが大原則です。近年、風水害などの自然災害の規模や範囲が以前よりも大きく激しくなる中、逃げ遅れによる犠牲にならないよう、自身による主体的な避難が重要になります。
そのためには平常時からハザードマップなどで地域の危険性を確認し、「いのちを守る行動は何か」を考えておくことで、災害発生時の適時適切な避難が可能になります。
「ペットのマイ避難カード」は、カードを作成することで、災害時のシミュレーションを行い、「だれが」「いつ」「どこに」「どのように」行動するのかを事前に決めておくことで、いざというときの避難行動に役立てることを目的としています。
「ペットのマイ避難カード」の作成
カードの構成は、以下8項目となっています。 ★自分に必要な項目があれば足してもかまいません!
ペットと家族の避難カードとして、ペットや家族の避難行動について、記入していきましょう。
 |
★様式のダウンロードはこちらから ▶A5版(手帳貼付版) PDF 441KB ※ペット健康防災手帳に貼付 できるサイズになっています。 ▶A4版(掲示用) PDF 49KB ▶A4版(掲示用) Excel 22KB |
- まず始めに
- ハザードマップで自宅や周辺の災害リスクを確認しましょう。
災害リスクが高いものから順に作成していくとよいでしょう。
- 項目1:災害の種類
-
ここには、想定する災害を記入します。
例:洪水 - 項目2:発災時の状況
-
①自宅でペットと一緒にいる場合(自宅でペットと一緒に被災)
②飼い主は外出し、自宅にペットだけでいた場合(自宅にペットだけで被災)
③飼い主と一緒に外出している場合(外出時にペットと一緒に被災)
この3パターンを検討します。まずは①から検討してみましょう。 - 項目3:確認!
-
どこから情報を入手するのかを記入します。
例:テレビ・ラジオ、ひょうご防災ネット(アプリ) など - 項目4:だれと?
-
ペットは誰と避難するのかを記入します。
また、ペットの必要な持ち出し品は誰が担当するのかなど、ペット以外の分担も一緒に記入できるとよいでしょう。
例:長女が〇〇(犬)を担当
父と長男が家族の持ち出し品を担当
母が〇〇(犬)の持ち出し品を担当 など - 項目5:いつ?
-
どのタイミングで避難するのかを記入します。
例:警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が発令された時 など - 項目6:どこに?
-
事前に確認した指定避難場所や避難所を記入します。
ペットと一緒に避難することが可能かどうか、避難場所や避難所への安全なルートなども事前に確認しておきましょう。
また、明るい時と暗い時を想定して記入します。
例:昼(明るい時)●●小学校(浸水想定区外)
夜(暗い時)雨量を見て●●小学校へ。危険な時は自宅2階へ など - 項目7:どのように?
-
誰がどのように避難するのかを記入します。
この項目も、明るい時と暗い時を想定して記入します。
例:昼(明るい時)長女→〇〇(犬)をクレートに入れて、徒歩で●●小学校へ
父・長男→家族の持ち出し品を背負って、徒歩で●●小学校へ
母→〇〇(犬)の持ち出し品を背負って、徒歩で●●小学校へ
夜(暗い時)雨量をみて昼と同様に行動する。
危険な時は家族全員と〇〇(犬)は自宅2階へ など - 項目8:その他(メモ)
-
上記7項目で記入できなかったこと、補足などを記入します。
例:自宅が浸水想定区域(1~2m)
■■川沿い、アンダーパスは避ける など
「ペットのマイ避難カード」記載例
この記載例は、あくまで想定です。
自身や自宅などを取り巻く状況を確認して、その状況に合った内容をカードに記入していきましょう。
いざという時に迷わず行動できるように、様々な状況を想定しておくことが助けになります。
人用(ペットを含まない)の「マイ避難カード」の作成方法については、兵庫県ホームページからもご覧になれます。
▶兵庫県災害対策課「兵庫県ではマイ避難カードの作成を推進しています」